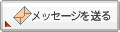■EL34について
EL34は6CA7といった方が60才前後の自作マニアにとってはしっくりくると思うのだが、最近はEL34がポピュラーなので一般的には逆に6CA7ってなんだということになっていると思う。
私が10代のころは中学校や高校のPAのほとんどが6CA7だったのでこの球は丈夫で大出力というイメージがある。大型管としてはEL34の他にKT88があるが当時は高価で入手も難しく大型管は6CA7と6L6GCが定番であった。
大型管を使ったハイパワーアンプは現在でも自作マニアの目標のひとつでもあり、頑張って挑戦してみることにした。
■EL34プッシュプルアンプ概要
どのようなアンプにするか構想するために過去の名機を調べて参考にした。一般的に名機と言われているアンプは以下の物と思う。
1953年 クオードⅡ (KT66プッシュプルクオード型)
1957年 ダイナコ MKⅢ (6550プッシュプルアルテック型)
1958年 ダイナコ ST-70 (EL34プッシュプルアルテック型)
1959年 マランツ #8 (EL34プッシュプルムラード型)
1961年 マランツ #8B (EL34プッシュプルムラード型)
1961年 マッキントッシュ MC275 (KT88プッシュプルクロスシャント型)
発売は今から50以上年前である。
クオード型は個性的すぎて改良の余地がない感じがする。マッキントッシュはトランスが特殊で追試はなかなか難しそうだ。現在の自作マニアに支持されている回路はのはマランツ8Bに採用されているムラード型だろう。初段をSRPPにしたり、ドライバー段までを低インピーダンス化したものなどバリエーションがある。さらにムラード型の発展型として差動2段ドライバーや出力段まで差動増幅回路にした全段差動アンプも人気がある。
ダイナコについては名機という範疇になるかわからないが、当時ベストセラーであったことは間違いない。片チャネル真空管3本で構成されていてsimple is the bestとしか表現できない潔よさがある。
海外では現在でもダイナコのドライバー基盤やトランスなどのクローンパーツが販売されていてアマチュアに人気がある。ダイナコの回路図は色々な書籍にもあるが、当時のインストラクションマニュアルがPDFでダウンロードできる。
現用の2A3PPアンプがムラード型なのでEL34PPアンプはアルテック型のダイナコST-70をモデルにする。
実機は見たことはあるが音は聞いたことがなくどのくらいの実力か不明だが、次の構想を基に現代風ST-70アンプ(以下本機)を製作した。
・電解コンデンサを1個も使わない電解コンデンサレスアンプとする。
・出力は両チャネル稼働で35W以上を目標とする。
・負帰還は、ダンピングファクタが5以上となる値まで掛ける。
・位相補正を出力段で行う黒川式としなるべく広帯域になるようする。
■各部の検討
(1)電源部
ST-70のB電源トランスの規格は360V×2・300mAで整流には5AR4が1本使われている。静止時の全電流は約210mAなので、5AR4の最大出力電流250mAからすると、余裕があまりなく大出力時はやや苦しいと思われる。
整流直後のケミコンの容量は30μFで整流管にやさしく、インダクタンスが1.5mHと小さいながらもチョークコイルを使っているのは良い設計と思う。また、ヒーターの6.3Vはコンデンサを介してアースに落とし、ドライブ段のH-K間の耐圧問題を解決している。
ST-70の一番の弱点は電源部と思うが、実際に海外のダイナコリペアーパーツ販売サイトでもST-70電源強化用のコンデンサが販売されている。
本機の電源トランスには出力35Wを確保できそうなものからハシモトのPT-270を採用し、320V×2をギュレーションと発熱の面からダイオード整流とした。
一般的にダイオードによる両波整流は電源電圧の3倍以上の耐圧のダイオードを使うことになっているが、管球アンプによく使われるIN4007、UF4007等1,000V耐圧のダイオードでは規格ぎりぎりで危ないので、1,200V耐圧のショットキーバリアダイオードを採用した。平滑回路はチョークコイルを使わず、FETとツェーナーダイオードによる簡易型のリップルフィルター兼定電圧電源を組み込んでいる。B電圧は400Vである。ヒーターはST-70と同じくフィルムコンデンサ1本でアースに落としている。近年のアンプは初段のB電源を抵抗で分圧して数10Vの電圧をヒーターバイアスとする方法が主流だが、電解コンデンサを使わないこの方法を採用した。
(2)出力段
ST-70の出力段はEL34のウルトラリニアー接続によるプッシュプルで上下共通でバイアス電圧を調整できるようにした固定バイアスとなっている。
出力トランスはA470という品名でインピーダンス4,300Ω、外形は高さ88 mm、幅75 mm、奥行き101 mmで割と大型のトランスである。カップリングコンデンサの値は0.1μF、グリッドリーク抵抗は270kΩである。
ST-70の製作マニュアルに記載された静止時のB電圧は415V、EL34のグリッド電圧-32Vとなっている。アイドリング電流測定用の15.6Ωの電圧を1.56Vになるように調整するとアイドリング電流が50mAになる。
本機はペアーチューブを使うことを前提にST-70と同様の固定バイアス回路とした。これは、ドライバーから見ても上下の出力段が同じなるので都合がよい。
出力トランスにはノグチトランスのPMF-60Pを採用した。一次インピーダンスは5,000Ω、UL接続タップ付で外形は高さ103mm、幅86mm、奥行き93mmでA470とほぼ同じ大きさである。インダクタンスが不明なのだが「真空管式プッシュプルアンプ」(松並希活)の製作例”6L6GCプッシュプルパワーアンプ”を参考にしてカップリングコンデンサを0.1μF、グリットリーク抵抗を240kΩとした。
(3)ドライバー段
ST-70の初段とドライブ段は7119という複合管一本だけを使ったシンプルな構成で最も気に入っている部分だ。7119は通販ではほどんど入手不能、秋葉原の真空管専門店の店頭には置いていたりするがかなり高価だ。ST-70のドライバー段兼位相反転回路はPK分割回路で負荷抵抗は47kΩ+47kΩ、電源電圧は375Vである。
本機ではピン配列は違うが入手が容易で安価な複合管6GH8Aを採用した。ST-70は80年代に一度復活したことがあるが、この時に使われていたのは6GH8Aであった。6GH8Aの他に6BL8や6U8が使用できる。負荷抵抗をST-70と同じく47kΩ+47kΩ、電源は出力段と共通にして400Vをかけている。
6GH8Aの3極管のプレート電圧の最大定格は330Vだが、「オーディオ真空管マニュアル」(一木吉典)によるとCR結合増幅回路では定格の2倍の電圧をかけられるとあり、問題はない。
一般的にPK分割位相反転回路は出力電圧が低くバイアスの低い球向けの回路だが、本機は実測でPtoP値が120V以上あるのでバイアス電圧32VのEL34は十分ドライブできる。

(4)初段
ST-70初段の5極管の負荷抵抗は270kΩで次段の3極管と直結でCRによる位相補正回路が入っている。この回路ををシミュレーションソフトで解析すると高域のカットオフ周波数は約6.3kHzで、位相補正回路を外すと120kHzとなる。PK分割位相反転回路はミラー効果の影響がなく前段の高域特性が良くなる特徴がある。
ST-70のスクリーングリッドの電源は1.5MΩの抵抗一本で供給されていて0.05μFのバイパスコンデンサをカソードに接続したシンプルな方法になっている。また、B電源からカソードに330kΩの抵抗が接続されているが、ここに流れる電流でカソード抵抗を小さくし、電流帰還によるゲインの減少を小さくすることでバイパスコンデンサを省いている。さらに、B電源に含まれるリップル電圧をカソードに注入することによりハムのキャンセルを行っていると思われる。
本機では出力段が第1ポールになるように位相補正回路を外し初段の負荷抵抗を小さくして高域を伸ばすようにした。シミュレーションの結果より負荷抵抗を100kΩとすればカットオフが200kHz以上になるので初段の負荷抵抗は100kΩとした。
スクリーングッドは36Vのツェナーダイオードでクランプし、ツェナーに流れる電流をカソード抵抗に流すことでカソード抵抗を小さくしてST-70と同様にバイパスコンデンサを省くことにした。
この構成でドライバー段までのゲインは実測で約110倍、高域のカットオフは約250kHzである。出力段のカットオフは80kHz程度であるので、出力トランスの一次側にCRを入れた黒川式の位相補正回路を採用して、NF抵抗にCをパラレルに入れた通常の微分型位相補正も併用した。
以上の検討により、決定した回路を図に示す。
・増幅部回路図
・電源部回路図
[次ページに続く]