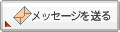■6V6について
私が小学生だった昭和40年代はラジオはすでにトランスレスで出力管は30A5や35WC5といったものが定番でした。トランス付きのラジオを見かける事はほとんど無く6V6GTなどのGT管はあこがれの存在でした。
ふと聞いたモノラルテープレコーダーの迫力ある音が忘れられません。出力管は6V6GTでした。今でもオークションでたまにGT管が整然と並んだアメリカ製のアンチックラジオを見かけるとホントにかっこいいと感じます。
私の中ではGT管は「禁断の惑星」のロビーのイメージなのです。
■6V6シングルアンプ概要
10年以上も前に買ったトランスや真空管がデッドストック状態になっているので陽の目を見させようと重い腰を上げました。
電源トランスはタンゴのN-12、出力トランスはタムラのF-475です。真空管はBENDIXの5992とフィリップスの6SL7、その後購入したエレハモの6V6GTも所有しています。
今回はシンプルで小型化を目標にチョークコイルを使わないアンプを考えました。また、ご自分で設計出来ないビギナーの方がこのアンプを参考にコピーを作成しても容易に成功するように電源にトランジスタを使わない回路にしました。
B電源はチョークコイル、FETを使わずCRリップルフィルターのみとすると抵抗器での電圧降下が大きくなるため整流管は採用できず、ダイオード整流にしました。
整流、平滑後の直流電圧やリップル電圧がどの位あるかは表を使ったり計算をして大体の見当が付けられます。ぺるけさんのホームページに計算方法が解説してありとても参考になります。
しかし、計算はかなり面倒です。私はDuncan's Amp PagesからPSUD2という電源シミュレーションソフトを使って設計しています。このソフトは非常にシンプルで使いやすく良くできていると思います。トランスの内部抵抗やコンデンサのESRなども設定ができるのですが、ここはデフォルトのままで十分です。
残留雑音はなるべく少なくしたいのでCRフィルタを3段重ねました。3段目のCRは左右別にして低域のクロストーク対策をしています。ケミコンは手持ちの基板用を使いました。最近はブロック型よりこのような基板用のものが入手し易いようです。
アンプ部は初段を6SL7のSRPPとしてなるべく広帯域にし、さらに回路内に時定数を持ち込まないように下側のカソード抵抗をLEDにしてケミコンを省きました。赤色LEDの順方向の立ち上がり電圧(Vf)は2V弱なのでこの用途にぴったりです。また、負帰還用の抵抗も47Ωと小さくして電流帰還でゲインが少しでも低下しないようにしました。
 出力段とのカップリングコンデンサーは音質に定評があるASCを使いました。値は0.33μFとして6V6のグリッドーリーク抵抗(270kΩ)との時定数を出力段より大きくしています。
出力段とのカップリングコンデンサーは音質に定評があるASCを使いました。値は0.33μFとして6V6のグリッドーリーク抵抗(270kΩ)との時定数を出力段より大きくしています。出力トランスのタムラのF-475は前作の2A3PPアンプで使ったF-782と同じく大昔から販売されている物です。F-475は一次側の巻線抵抗が514Ωと大きく、巻数がかなりあるようでインダクタンス値が43Hもあります。内部写真
出力段の6V6は少しでも出力が取れるよう標準五結(ビーム管接続・自己バイアス)にしました。ここでのカットオフ周波数は計算上約16Hzになります。
多極管は何らかの局部帰還をかけるのが定石なので、トランスのNF巻線を使ってカソード負帰還を掛けました。通常、NF巻線は電流を流すように設計されていないと思われるのでパイバスコンデンサーで交流分のみを帰還しています。このコンデンサーの値も十分大きくして出力段の時定数より大きくしました。
さらにオーバーオールNFをスピーカーの16Ω端子から初段に戻しています。
NF巻線を使ってカソードNFを掛けると二段構成でも非反転アンプになり都合が良い事になります。
スクリーングリッドには1段のCRフィルターを通して電源を供給します。スクリーングリッドをプレートと共通にするとリップルがスクリーングリッドを通し増幅されハムが発生するからです。
出力トランスの一次側での電圧降下が約20Vもあるのでスクリーングリッドとプレートを同じ電圧にするCRフィルターの抵抗値は約4kΩになります。このフィルターでリップルが十分に取れるので初段のプレート電圧も共通にしました。
6SN7、6V6GTともヒーターは並列にして供給しています。誘導ハム防止のヒーターの接地は初段がSRPPのため単純にアース出来ません。通常はヒーターバイアス電圧を掛けるのですが、フィルムコンデンサーでヒーターの片側をアースする方法にしました。昔の海外メーカー製アンプによく見かけたやり方ですが、ハムもなく良好に動作しています。
■調整と測定
無帰還時のダンピングファクター(DF)は0.15です。周波数特性は-3dBが20Hzから25kHzで高域が予想外に延びません。
ここでカソード負帰還を掛けるとDFが1になり周波数特性も高域が40kHzまで拡大しました。負帰還量は約6.5dBです。さらに特性改善のため初段からオーバーオール負帰還を5.5dBかけました。これで周波数特性が10Hz(-0.5dB)、62kHz(-3dB)、DFは2.6となりました。
もう少しDFを改善したいのですがゲインに余裕がないのでこれで最終特性にしました。
8Ωのダミー抵抗を負荷にして10kHzの方形波を入力するとオーバーシュートが僅かに出ます。コンデンサーを並列に入れるとリンキング発生します。しかしダミー抵抗を取り去って容量負荷にしてもリンキングが多少大きくなるものの発振することはありません。容量を大きくすると波形が丸くなります。
周波数特性を超高域まで測定すると130kHz付近にピークがあります。位相補正を行うと波形を整えることが出来ますが、オーバーオールの帰還量が少ないので位相補正は行いませんでした。
また、音を聞いてもおとなしい音なのであえてこれ以上個性を無くさない意図もあります。
・出力:3.5W+3.5W
(8Ω、目視によるクリッピングポイント)
・周波数特性:10Hz(-0.5dB)~62kHz(-3dB)
(1Vを0dBとして測定)
・DF:2.6(1kHz、ON/OFF法)
・残留雑音:左 => 0.3mV 右 => 0.3mV
(入力ショート、ボリューム最大、8Ω負荷 0.3mVフルスケール交流電圧計で測定)
[次ページに続く]