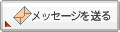■2A3について
2A3シングルアンプを作ったのは20歳位の時だったように覚えています。ケン・オーディオからキットを購入して回路はオリジナルで組んだものでした。当時はRCAの2A3は一本5千円くらいで容易に入手できたので何度も組み直してかなり楽しんだ記憶があります。最終的にはyahooのオークションで処分しましたが今思い出すとやはりたっぷりとした音質だったように思います。
■2A3プッシュプルアンプ概要
お小遣いが少し貯まったので予算を10万円以内として本格的な物を作る決意を固めました。
久しぶりに工作をするので、見栄えのする2A3のプッシュプルアンプに決め、あまり凝らないオーソドックスな回路で2A3の良さを最大に引き出す事を目標にしました。
とはいえ電源は少し凝っています。寿命があり、電子部品なのに中に液体が入っていることが何とも嫌な電解コンデンサーを一個も使わないオールフィルムコンデンサー仕様としました。 このためFETによる定電圧電源回路を導入し同時にチョークコイルも省きました。
電源トランスは市販のトランスに適当な物が無いので特注しました。トランスの実装はシャーシーにべったりくっつけてもよいのですが、発熱対策のためナットで浮かして取り付けました。
電源回路は前段と出力段を別巻き線にしてファーストリカバリダイオードでブリッジ整流しています。定電圧電源は前段用の電源からツェナーダイオードと定電流ダイオードで基準電圧を作りFETのゲートに加えています。基準電圧からゲートの間にCRフィルターを入れ電圧がゆっくりと立ち上がるようにしました。パワーFETはフルモールド型の2SK2847で取り付けが楽です。発熱を押さえると共にクロストーク対策のために左右別々にしてシャシーの裏パネルに直付けしました。

アンプ部分はオーソドックスなムラード型で出力段は固定バイアスです。初段は内部抵抗が低い割にはμの大きい12AT7を採用し調整のしやすいSRPPとしてカソードのパイパスコンデンサー(ケミコン)を省きここでの時定数を無くしました。ドライバーは無理が効く12AU7を採用、B電圧を400V(実質300V)かけて何とかドライブ出来るようにしましたがドライブマージンはほとんどありません。
当初は前段に6DJ8-6CG7のラインナップを考えたのですが、電源トランスが意外と小さかったので省エネを第一にして12AT7-12AU7に決めました。
12AT7はSRPPとして出力インピーダンスを低くしてるのでドライバーの12AU7の入力容量の小ささと相まって高域が延びています。また、12AU7は内部抵抗が低いので20kΩ台の負荷抵抗と合わせた出力インピーダンスも低くなり、2A3の入力容量が100PF弱あったとしても高域は数百kHzまで延びます。黒川式ほどではありませんが広帯域なアンプになっています。
2A3のフィラメントは、これまでの経験や過去の諸先輩の作例からハムは1mV以下に出来ると判断して交流点火にしました。
ハムバランサーは調整しやすいように10Ω固定抵抗と10ΩVR、22Ω固定抵抗を直列に入れています。当初22Ω+10ΩVR+22Ωで作製しましたが、VRを回しきってもハムバランスが取れなかったため片方の固定抵抗を10Ωに変更しました。ここは50ΩのVRのみでも良いかと思います。組み合わせの問題で解決はしますが、フィラメント巻き線4回路用意するか、バイアス回路を4回路用意する方が調整は楽で完成度が高くなると思います。
■調整と測定
2A3はペアで購入しましたが、僅かにぱらつきがあり、DCバランスが取れてもハムが取れない物があり調整はかなり面倒です。DCバランスが取れない組み合わせがの方がかえってハムが取れたりします。また、2A3が完全に動作状態(4,5分掛かる)になり熱くならないとハムが取れないし、バイアス電流の違いによってもハムの打ち消しのポイントが変わってきます。
出力トランスの巻き線抵抗が75Ωなので、電圧降下が3V(約40mA)になるようにバイアスを調整しました。
残留ノイズは0.15mVまで追い込んだのですが、裏蓋をはめると誘導のためノイズレベルが上がり最終的には0.5mV程度になりました。エレハモ12AT7-GOLDもバラツキがあります。指ではじくとマイクロフォニックノイズも出ます。数本買って選別した方がよいでしょう。また、12AT7に手を近づけてもノイズレベルが変化します。
無帰還時のダンピングファクターは1.6程度です。DFが5になるまで8dBの負帰還を掛けました。
8Ωのダミー抵抗を負荷にして方形波を入力するとオーバーシュートが出ますがリンキングはほとんど出ません。コンデンサーを並列に入れるとオーバーシュート、リンキングが僅かに大きくなりますが発振はしません。ダミー抵抗を取り去って容量負荷にしても発振しません。
使用したF-782は古いタイプの出力トランスで当時は20dBの負帰還が当たり前だったのでこの時代に高帰還に耐えられるよう設計された出力トランスは8dB程度の負帰還ではビクともしないようです。
このままでも良いのですが、気持ちが悪いので僅かに位相補正を行いました。
まず、トランスの2次側にCRを直列にした補正抵抗を入れましたが、オーバーシュートの大きさは変わりません。そこでこの補正方法はやめて、通常の微分型補正で調整しました。1kHzの方形波を入力してダミー抵抗のみの負荷でオーバーシュートが出ないように、22PFのコンデンサーを負帰還抵抗に並列に入れました。ダミー抵抗にコンデンサーを並列に入れるとオーバーシュートが現れます。10kHzの方形波を入力してダミーロードのみの場合は少しオーバーシュートが現れます。並列にコンデンサーを入れるとオーバーシュートが大きくなります。さらに、抵抗を外し容量負荷にするとオーバーシュートとリンキングが現れますが発振はしません。もう少し強く補正しても良いのですがせっかくの高域特性を生かすためにこの値としました。
逆に入力にローパスフィルターを入れた方が良いのか迷う所です。現在はLPFを入れていません。
・出力:15W+15W
(8Ω、目視によるクリッピングポイント)
・周波数特性:10Hz(+0dB)~130kHz(-3dB)
(3Vを0dBとして測定)
・DF:5(1kHz、ON/OFF法)
・残留雑音:左 => 0.5mV 右 => 0.5mV
(入力ショート、ボリューム最大、8Ω負荷 0.3mVフルスケール交流電圧計で測定)
[次ページに続く]